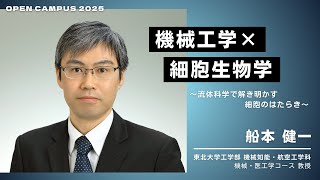生体内微小環境の流動・輸送現象を再現する間質機能チップの開発
生体内微小環境の流動・輸送現象を再現する間質機能チップの開発
- 概要
生体組織を構成する細胞は間質と呼ばれる組織に包まれており、細胞の動態は間質内の流動・輸送現象に伴う刺激により変化する。しかし、間質内の微小環境に応じた細胞動態については不明な点が多く、疾患の治療・予防の限界の原因となっている。局所的な培養環境を能動的かつ即時的に制御しながら細胞観察を行うことは困難であり、近年盛んに研究が進んでいるマイクロ流体デバイスを用いた手法においても、培養環境制御は十分ではなかった。このような背景の下、間質内の環境因子として酸素濃度・pH・間質流に着目し、それらの場を素早くかつ厳密に制御しながら、個々の細胞の即時的な応答と細胞間の相互作用のリアルタイム観察を可能にする「間質機能チップ」を開発した。
- 従来技術との比較
培養環境を制御しながら細胞動態の経時的観察を行うために、顕微鏡上に設置して細胞周囲の環境を制御するステージインキュベーターなどが用いられてきたが、局所的な培養環境の変化を能動的かつ即時的に制御することは非常に困難であった。また、マイクロ流体デバイスやorgan-on-a-chipを用いることで、微小環境を制御しながら細胞動態を観察する方法が近年盛んに研究されているが、培養環境制御の観点では十分ではない。本チップは、細胞実験に適用することで、厳密かつ迅速な環境制御の下で細胞動態の観察を実現する。
- 特徴・独自性
-
間質機能チップ内には細胞培養用の流路を配置し、それらの鉛直上方に複数のガス流路を配置した。酸素と二酸化炭素濃度を調整した混合ガスをガス流路に供給することで、ガス交換により細胞培養用の流路内の酸素濃度とpHの制御を実現した。既存の化学反応を利用する方法に対して細胞毒性がなく、酸素濃度とpHを自在に制御することが可能になった。また、細胞培養用の流路をハイドロゲルで満たし、その出入口に培養液の水頭差を与えることで間質流の制御も可能である。開発したチップ内で細胞を培養し、酸素濃度・pH・間質流を制御しながら細胞動態を観察することで、それら環境因子に対する細胞の応答特性を解明することができる。
- 実用化イメージ
-
がん微小環境や炎症性微小環境などに特徴的な低酸素・低pH環境を再現した上で、薬剤の効果を事前評価し、効果的な薬剤の選定と容量の決定に利用できる。また、基礎医学や生物学的な研究において、培養環境の厳密制御下の細胞観察を行う実験システムを提供する。
- キーワード
研究者
流体科学研究所
船本 健一 教授
博士(工学)(東北大学)/修士(情報科学)(東北大学)
Kenichi Funamoto, Professor


 医療・創薬・医療機器
医療・創薬・医療機器
 情報通信
情報通信
 環境
環境
 ナノテクノロジー・材料
ナノテクノロジー・材料
 エネルギー
エネルギー
 ものづくり・機械
ものづくり・機械
 社会基盤・安全
社会基盤・安全
 フロンティア・宇宙
フロンティア・宇宙
 人文・社会
人文・社会